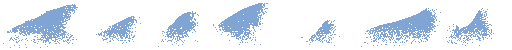
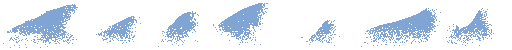
 浅生の釜池 つぶら池
浅生の釜池 つぶら池
(上市町)
上市町、大岩山日石寺の裏山で、昔からハイカーによく知られた高峰山の
手前にある人工のため池である。
その周辺には鍋冠山がシンボルとしてあり目標になる。
最近はこの水源を利用する水田が無くなり、その後どうなっているのか解らない。
つぶら池や周辺の湿地帯には特有の植生界があり、自然環境の変遷が勉強できた。
以前は県定公園として多くの人が訪れてルートもはっきりしていたが、30年ほど前に
杉の植林が行われてから行っていない。周辺がどのように変わった確かめたい思いもあり
今回は春に尋ねるに当たっての下見に歩いてみた。
2019年追記
以前県指定公園だったが、いつのころから解除されている。周辺に林道が付き水源地が分断された為か
以前にあった沼地が空池に変わり、一年中湧水が出て居た所も水枯れするようになった。
そのような周辺の変化で植生が変わった。
| 平成19年2月4日 | 平成19年3月4日 | 令和元年5且23日 (平成31年2019年) |
| 浅生林道で釜池方面へ(途中まで) | 釜池とつぶら池を周回 | 新緑の森と湖を尋ねて2019 |
平成19年3月4日
釜池 つぶら池
数十年ぶりに釜池に向かった。林道には既に雪もなくつまらないので、右側にある尾根に出て
雑木林の残雪を拾いつつ尾根通しにショートカットして行く、雑木林の中を自由に歩く。
尾根を次ぎ次と乗り越え、釜池まで最短距離で向かうが小山がいくつも有り、同じような所が出て複雑な
地形が迷いを誘う。尾根の頂上に登り地形を確認してまた進む。
これがおもしろい。この時期だけの冒険だ。全体象は把握していても細かな所で新たな体験が出来る。
くたくたに疲れるが、冒険心を大いに満足できる。
| 10:30 高峰山への林道の入り口には一台のジープがあった。 さらに奥の林道には倒木があり進めない のでその手前に軽四が止めてあった。 その少し先の岩のごつごつしている所で 右側の斜面を登る。 |
|
| 11:05 登ると一面の残雪だった。 そこでは先が見えるので 目標の方向に向かって歩く。 カンジキハイクの始まりだ。 |
|
| 小さな丘や雑木林を(コナラ)ぬけると 窪地がありその周囲に林道が通じている。 (地図には無い) 私が進む方向と同じ向きにカンジキの跡が 残されている。 1.2週間前の物だろうか? 同じ事を考えている人が居たのだろうか? |
|
| 林道は山間の窪地を曲がりくねって続いている。 そこをショートカットして行く |
|
| 11:24 反対側から ここの窪地は空池になっているのか? 以前義父にここへ案内して貰ってこの池でミズゴケを採ったことがある。その当時は池だった サツキ盆栽に使うためにわざわざここへ来たのだった。 それがいつの間に林道が付き業者がトラックを横付けにして採って行ったことを思っていた。 |
|
| やはり林道は、くねくねと迂回している。 地図にも載っていないのでので、何処に 向かっているのか見当も付かない。 初めから林道を思っていなかったので、それを 無視し、直線的に正面の尾根を見上げて雪の 付いている鞍部に向けて登り、山腹をトラバース。 尾根の上に出ると又先に窪地が出てきた。 左の丘には杉の人工林があり、おそらく林道は その裏に続いているのだろう。 |
|
| あえてそこに向かわず反対の山腹に雪を 拾って前方に行くと、先行者の足跡も同じ ところにあった。 かなりの斜面であり、こんな複雑な山間を 全く同じ所を歩いているなんて予想を越えて いる。 私と同じ事を考え実行している人が居たのだ! |
|
| 尾根を乗り越し別の窪地を過ぎると またまた林道に出会った。 (高峰林道ならば何度も通過している ので解る、やはり地図にない違う物だった。) その林道を横切って急斜面に取り付き 一際高い尾根に登る。 地図上でも多くの起伏がある |
|
| 12:00 登り着いた尾根を山頂に向かい 周囲の山を確認する。 鍋冠や高峰山が確認できた。 山頂は杉林で間伐の枝打ち作業の跡が 残っていて窓のように視界があった。 東側に下れば高峰山への林道だろう。 |
|
| 12:20 山頂から雪を拾って南側に下ると 三度、林道に出た。 するとまた先行者の跡が残されていて、 再び同じ方向に歩く。 |
|
| 12:25 その林道を少し行くと右手に 釜池への標識を発見。 それに従い行く。 (高峰山方向からは逆になる) しばらく行くと一気に下り小さな尾根を 乗り越すと釜池がみえる。 |
|
| 釜池 窪地をうまく利用して水を貯めている。 斜面を池に下り始めると。鴨の群れが 一斉に飛び立ち、静かな山間に30羽位 の鴨の飛翔する音がこだまする。 窪地からの飛び立ちは時間が掛かる のだろう円を描いて徐々に高く離れて行き 、やがて姿が見えなくなった。 まるで伝書鳩のようだった。 |
|
| 12:49 池に降りると、湖面の一部だけに水面が 現れていてそこに鴨が羽を休めていたのだ。 南に面した堤は雪もなく乾燥している。 カンジキをぬき昼食タイム。 堤は雑草が刈り払われていて手入れが されている。 ぽかぽかとた日差しに身体をさらし、ゆっくり 景色を眺める。 湖面は殆どが氷に覆われ、白く太陽の光を 反射しているのみで全くの静寂だった。 |
|
| 13:50 堤の中央に排水口があり、出口は絶壁で 滝のように流れ出ている。 (大岩川源流) その高台に立ち、前回の到達場所を確認し 下山ルートを目視する。 身支度をし、目的のもう一つ、ぶら池に向かう。 |
|
| 13:53 再びカンジキを履き尾根を乗り越す。 峠から釜池の全体像を撮る。 |
|
| 尾根を反対側に下ると 湿地帯があり雪解けの水が小川を 作っている。 この湿地も以前は池であり徐々に植生が 変わり ネコヤナギが繁茂していた。 (以前は池の名前もあり地図に載っていた) 現在は池の形が無くなり、中央に小川が 残るのみで春には水芭蕉が咲く ここにも先行者のかすかな跡が 残されている。 |
|
| 14:03 そこを反対側から撮る。 |
|
| さらに又一つ尾根を越えると つぶら池に着く。 広い湖面には一面に氷が張り 広場になっている。 先行者の足跡も氷の手前で消え真っ直ぐに 湖面を渡った事を示している。 私も氷の上をあるいて見たが大丈夫だった。 しかし、対岸の一部で薄い所があり安全の ため戻り、迂回して対岸に渡った。 |
|
| 14:18 つぶら池 春には珍しい浮島などが見られ、周囲の 湿地帯には珍しい景色が出現する。 この辺り一面は湿地帯で特有の 植生が見られる。 (一時期、県定公園に指定されていた。) 対岸に渡ると、かすかに足跡が続いている 対岸からの写真(鍋冠山が背後に見える) |
|
| いよいよ最後の下り 以前の登山道があるのかどうか解らないが 地形を見ながら残雪を拾ってグングン下る |
|
| 下ると、前回に来て休憩した地点に出た。 (つぶら池と釜池への分岐地点) 既に雪も融けて夏道が出ていたので ルンルンで下る。 かすかに登山道が残っている。 |
|
| そこから下部には雪もなく夏道らしき物が 川に沿ってあった。 僅かな標高差でこんなにも違う おそらく100M位の差異があるか 無いかだろう |
|
| 林道の橋も無惨に放置されたまま 朽ちていた。 |
|
| 14:41 前回と同じ所から |
|
| やはり前回と同じ所から | |
| やはり廃道は倒木が覆い道は 徐々に失われて行く。 前回の廃道をてくてくと戻る。 谷を大きく迂回するといよいよ道も 雑木で煩わしくなってきた。 |
|
| 林道を途中で右にショートカットし 杉林の際を登り尾根を越える。 尾根の鞍部にある笹林で、山鳥がいきなり 「バタバタ!!」 と足元から飛び出しびっくり。 山鳥は人が近づいてもなかなか逃げない いよいよ1M以内になってから爆音を立てて 飛び出るので本当に驚くのだ。 おどろいたのなんの! 心臓が飛び出るのだ! 反対側に下り、その後は人工林の中の 林道を下る 上浅生部落に出た。 |
|
| 15:15 爽やかな田園風景が待っていた。 林道を種方面に歩く |
|
| 15:40 林道の入り口に着き 今回のハイキングを終える。 |
林道に下ると既に春を待つばかりの里山だった。
今回は、全く同じルートを歩いた人が居た偶然に驚き、何かしら先行者に親しみを感じる。
どんな人が何を思ってこのルート歩いたのか、会って話がしたくなってしまう。
さて、今回も結果的に先行者の足跡を踏破する散歩に終始したが、里山歩きを充分堪能した。
高い山に気持ちが向きがちではあるが、里山の良さは決して劣らない。
放射冷却現象で早朝冷え込んだ朝などは、スタスタと雪面を自由自在に歩ける。
まるで世界が違って、すごく楽しみが増える。今度はそんな日を狙って出かけたい物だ。

2019年5月23日
2019年5月23日
新緑の森と湖を尋ねて
定休日で快晴模様。天気予報では30度くらいの夏日を予報している。異様な暑さだ!。
11時頃、コンビニでカップラーメンとおむすびを買って西種に向かう。

 |
11:20 高峰林道に入り分岐地点に車を置いた。 この先も車で入られるのだが、目の前に泥んこの水たまりが見えていた。車を洗ったばかりで汚すのがおっくうでここへ止めた。 この先の広場に止めるのがいちばんよい。 但し車高の低い車は要注意。 |
 |
11:30 高峰との分岐。釜池方面に進みむ |
 |
11:40 すぐに作業林道に入り、緩やかに登って行く。一旦下って登り返した先が峠。 峠 木々が葉を広げているので此処からは湖面は見えない。 |
 |
12:00 その峠の急斜面を下ると釜池。 最近山菜取りの人達だろう足跡もある。 ここはため池なので管理されているので此処まではルートははっきりしている。 池を覗いても動くものは見られない。 魚でも話してあるのかな? 透明度は無い。 中央に水路の排出溝があり わずかに水音がしている。 |
 |
12:17 池を半周して反対側から尾根を目指す。 ここの雰囲気も良い 笹林の中に巨木が目立つ。鬱蒼とした森である。 |
 |
12:20 日影の尾根道にはユキザサやエンレイソウにサンカヨウなどが見られる。 |
 |
12:30 小尾根を越えて下ると一気に植生が変わる湿地帯。 (かつての池の跡地) さらに進むとそこから流れ出る小川がある。それに沿って下る。 以前は明瞭な道もあったが今は荒れて判らなくなった。 要は小川に沿って下るのみ。 |
 |
12:40 すぐに平坦な湿地に着く。 ここも池の一部で、堆積した草や土地で沼地になっている。 足元に注意しながら水草の上を進む |
 |
13:00 つぶら池 まさに神秘の湖 周囲500m位か全く人の気配のない池である。 池の縁は水草が厚くなっていて人も立てるが下は水で浮いているだけ。揺するとプカプカとうごく。 小さな青糸トンボが水草の周囲をつがいで飛び回っている。 ここはいつ来ても癒される場所だ。 しばらくそこにたたずみ池を眺めてから釜池に戻った。 |
釜池のいつも場所で弁当を食べる。日影でそよ風もあって気持ち良い。
ただ小さな虫が寄って来るので煩わしい。防虫スプレーを持ってくればよかったと後悔。
何時もは蚊取り線香を持ってくるのに〜
少しの山菜をザックにしまいつつ
ゆっくり弁当を食べて帰宅、全く人に出会わない一日だった。

浅生林道で釜池
平成19年2月4日 快晴
浅生林道をカンジキハイク。
前日の天気報では雨か雪のような良くない天気予報だったのに
それが朝起きると快晴の空だった。騙された見たい。
あわてて、ザックとカンジキを車に放り込み山麓へ走る。
上市町、大岩山日石寺の横に流れている渓流に沿って、急坂を行く。
車道に水を流し 川のように融雪している。スリップの心配も無く下浅生部落に着いた。
上浅生に向かうと融雪もなく普通の山道だが、除雪車が道を空けてくれていたのでラッキーだった。
今回は、前回行けなかった釜池まで行きたいとやって来たのだ。
今は廃村で住む人の居なくなった中の又、その先の大沢部落と桧谷部落へ通ずる旧道をたどる。
この道は大岩に又戻る周回道路で今は放棄されて荒れている。
ちょうど中間地点に釜池から流れ出る谷を跨ぐ橋がある。その谷を遡行してみようと思う。
| 11;00 ちょうど城ガ平山への反対側に当たる道路際に 車を止めた。 路面は凍結してつるつる。 日が当たると溶け始めるだろう。 |
|
| 廃道となっていている旧道に沿って くねくねと谷間を迂回している林道を行く。 雑木が茂り、いたる所で道を塞いでいる。 その雑木が雪の重さでトンネルになって いる。 うっかり触れるとすっぽりと雪の網を頭から 被らされる。 |
|
| しかし、雪が木々の枝先に残り 白く輝いてきれいだった。 日が差すとすぐに落ちて無くなる命 春の淡雪にも似て一瞬に輝く。 |
|
| 里山のこんもりした山並みが 新雪に覆われ見事に輝いている。 ここの辺りは人工林(杉林)が無く 落葉した広葉樹林の里山は 見晴らしが良い。 |
|
| おまけにここの林道は南向きなので 日が当たり暖かい。 |
|
| サクサクと雪を踏みしめる足音と カンジキの足跡を残しながら行く。 高い位置にある林道から谷間を覗き 対岸の山並みを見ながら地形を読む 地図と現在地を確認しながら |
|
| 夏にはおそらく通過が困難な山道も さすがに旧道の痕跡を残しているので 迷うことはない。 倒木が道を塞いでいたり 路肩が崩れていたり、上部からの 落石などで荒れている。 |
|
| 12:20 小さな尾根を越え再び大きく谷を迂回したら 目的の谷が見えてきた。 近くへ行くと橋が朽ちて落ちていた。 幅3M位の橋はぼろぼろに朽ち真ん中で折れ 谷の流れにつっぷしていた。 放棄されてずいぶんな時間が経っている ようだ。 この谷を遡行する。 その上に目的の釜池がある。 谷は降雪量が極端に少なく川が出ていて 中途半端でやっかいな積雪状態だった。 |
|
| 仕方なく川の上を大きく高巻きしながら 北斜面の日陰をラッセルして行く |
|
| 北斜面に着いた雪はふかふかで 時間を費やす |
|
| しばらくしてやや平坦なところで休憩する | |
| 谷間はさすがに寒いが 白銀の世界は格別の造形美に 心打たれる。 |
|
| 14:00 さらに進むと谷が狭まり いよいよ最後の登りが見えてきた。 それに合わせさらに急斜面と藪が覆い 被さっている。 ここまでが限度だった。 時間切れ。 |
|
| 改めて対岸を見渡すと きれいな山並みがあった。 熊棚が所々にあり、木々の枝が見事に 輝いている。 |
|
| 体制を整え下山を開始する。 ラッセルの跡をそのまま戻る。 |
|
| やはり下山は早い、30分位で林道に戻る。 林道の先、峠の立木が光を受けて 桜のような姿で輝いている。 その先にあった旧部落の中や棚田跡に 植えられた杉が大きく育っている。 それ位の永い時間が過ぎている。 |
|
| 林道に沿って戻りかけて振り向くと、路肩の 木が背景の山とマッチングしている。 前夜の新雪をこんもりと被った山の 頂上部の輪郭が光を受けて輝いている。 ちょうど振り向いた地点では、山肌から湧き出た 水が流れを作り道路を浸食している。 流れの周囲には雪もなく地肌を見せている。 そこに蕗のとうが転々と若草の色を見せている。 地下水は暖かいのだろう。 私はその一角の岩の雪を除けて腰をかけ 海苔のおむすびを食べた。実に美味かった。 太陽の暖かさもご馳走だった。 |
|
| 帰り道々、不思議な杉林を発見した。 こんもりとした森の一部に黒く異彩を放つ 杉林があった。 どうして? |
|
ウサギの姿を見ることはなかった 足跡が僅かにあったのみ ごく最近町はずれで日中、キツネを見かけた。 そんなことなど影響しているのかな? |