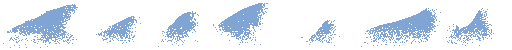
 城ヶ平山(茗荷谷山) 上市町大岩
城ヶ平山(茗荷谷山) 上市町大岩 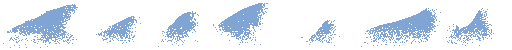
 城ヶ平山(茗荷谷山) 上市町大岩
城ヶ平山(茗荷谷山) 上市町大岩
| 2010年3月7日(日) | 2011年4月24日(日) | 2017年4月17日(月) | 2019年4月23日 |
| 郷土の歴史を訪ねる | 友人と山菜摘み散歩 | 友人に誘われて | 春山散歩 |
| 2021年11月29日 | 2023年9月7日 | 2024年1月20日 | 2025年5月14日(水) |
| お手軽散歩 | はげ山まで周回 | はげ山往復 | 友とはげ山往復&ソーメン |
この山は戦国時代の山城があったと史跡が残っている。周囲の山から独立した山頂からは平野部が見渡せて戦略的には
重要な位置だったと見られてる。
別名茗荷平山と名前が示す通り、旧集落跡地周辺には茗荷の群生が見られる。
(登山道)
登山口は大岩登山口と中浅生(花の家)からの2か所がある。どちらも時間的にはほぼ変わりなく、体力的には中浅生から
の方が楽である。中浅生登山口からはハゲ山へ登る事もできる。
一般的には大岩登山口から山頂を経て中浅生へ下る周回ルートが多い。
このルートは中浅生に花の家(古民家で一般開放されている。アニメ動画おおかみこども雨と雪のモデルとなった家)がありトイレ休憩が出来る。
下った先には大岩山日石寺に立ち寄り国指定重要文化財(大岩不動尊摩崖仏)を見学できる。また門前の食堂街で名物の山菜やソーメンが食べれら
るこ事もこのルートを選ぶ理由の一つである。
2025年5月14日
2025年5月14日
山友とはげ山往復とソーメン
体調不良を訴える山友とやって来た。原因は判らないが春の一過性の鬱かな?
そんな訳で遠征予定を止めて気分転換を図ることにした。春の山は新緑が心地よい。
 |
9:30 いつものように水公園駐車場からスタート |
 |
10:10 山頂は視界が良い。開放感に浸る。 トレイランの青年が追い越していった。 |
 |
11:00 峠山。 先程追い越していった青年が戻ってきて(早いね!)〜と声を掛ける。 |
 |
11:30 はげ山まで順調に歩いた。 先行者が一人。 私達が着くと交代するように下って行った。 ゆっくり休憩して軽く食事 13:00 中浅生への分岐辺りで、先ほど戻って行った青年が又登って来た。「聞くと」下の店でラーメンを食べたのてカロリーオーバーなのでもう一往復するのだと言ってハゲ山へ向かっていった! 凄い!! 先日まで工事中だった大岩川の登山口に戻ると、橋の袂に水道とブラシが設置されていてありがたく靴を洗う事が出来た。 登山者には嬉しいい事だ! |
 |
13:40 私達は軽く食事を済ましていたので、 階段を登り、大岩館で腹を満たす事に。 山菜の煮物、白玉、ソーメン、&ビール。 観光客が結構いて賑やかだった。 |
その後6本滝へ行くと西洋外国人の姿が多くビックリ!運動姿で軽装だ。
山門には多くのマウンテンバイクがあった。何かイベントがあったのだろう?。
その後、道路工事中の大観峰へ散歩して戻った。

2024年11月20日
2024年11月20日
はげ山往復
今回は自分の体力測定のような思いで、はげ山への往復を試みた。
出遅れたので、いつものようにコンビニ弁当を買い、大岩へ向かった。
 |
9;32 大岩川親水公園から歩き出す・ 登山口となる、バス停広場奥の橋が工事中で進入禁止の看板が見えている!。 あああ!!〜と思いながら近くまで行くと通行が可能だった。  |
 |
9;50 前を歩いていた男性に声を掛けて先に出ると、すぐに水場に着いた。 ここには今も畑や小屋があり、手入れに通っている人が居るのだ。 付近は棚田になっており水田跡地が幾重にも石垣によって仕切られている。 40年前くらいに集落ごと移住したと聞いている。 その跡地に杉の植林がされている。 当時はこの水場がいかに貴重なものであったろう〜 |
 |
水場から鬱蒼としたスギ林を回り込み、茗荷の群生地を登り切るとタイミング良くベンチのある尾根に出る。 一旦休憩を取る。 そこからやや傾斜が強まり冬椿の赤い花を見ながら進む。 10;09 しばらくで傾斜が緩み軽快に行くと、見晴らしの良い所にベンチがある。 富山湾が見通せ、夏場ならちょうどよい日影となる。 |
 |
10;23 山頂 誰もいない静かな山頂だった。 |
 |
海側の風景。見慣れた風景だが広大な視界に心癒される。 |
 |
同じく剱岳方面 あいにくの曇り空で、紅葉が今一さえないのだが、やはりいいね!! |
 |
|
 |
そのまま20分位進むと、登りつめた尾根の上に 「頑張ればあなたも行ける」 と書いた案内板があった。 昨年から見ていたが、新しくなっていた。 (進むと先程までいた山頂が見える窓。行き止まりで引き返す) 今回はパスして進む |
 |
10:44 中浅生へ下る分岐地点 周回ルートの場合はここを右に下って、花の家に立ち寄り、車道を下る。 今回はそのまま直進してはげ山へ向かう |
 |
10;58 尾根を回り込んで登り切ったら峠山 小さな台地をこえて下る |
 |
11:04 一気に下ると西種へ下る分岐地点。 はげ山のみを対象とするならばこの下にある水上集落から登る。 |
 |
11:16 はげ山に着いた。 一組が食事中だった。 話すと射水市からのご夫婦。良く来ておられるようで、はげ山新道や三角山などの話をしてくれた。 |
 |
まだ剱岳は見えていた。 食事をしていると、数人のランナーが来ては下って行った。 これから見えている千石城山まで走るのだと言っていた。 |
 |
12:42 再び城が平山頂に戻ると。 加賀市から来たという3人グループにルートの説明を求められた。 周回コースで戻るか来た道を戻るか迷っていたらしい。 高齢の男性が心配そうだった。 |
 |
剱岳の山頂は隠れたが、池の平から猫又方面はまだ見えていた。 |
 |
反対側も富山湾が見えて開放感がすばらしい! |
13:34 車に戻った。
体力がどこまで持つか、どこまで歩けるか?体力測定を兼ねた山行だった。
先々週から休まずに毎週歩いてきたので、やや苦しさが和らいだ感がある。
ヤマレコをセットして歩きだすと。やはり一人だとややもするとオーバーペースになりがちだった。
今回もややハイペースだったがコースタイム60%〜70%で歩けた。

2024年1月20日2021年11月29日
2021年11月29日(月)
山友とお手軽散歩に
快晴予報でたまらず、近くの山へお散歩。夕方3時には富山市内の歯医者に行かなければならなので、2時までには自宅へ
戻る予定で出掛けた。
 |
町内のコンビニで買い出し。 10:30 大岩親水公園駐車場へ止めて歩き出す 大岩バス停の奥にある公衆トイレ横には 「城ヶ平山登山口」と案内板がある |
 |
10:47 尾根に出る手前の木道が新しくなっていた |
 |
10:51 尾根に出ると、ここのベンチも新しくなっていた。 |
 |
12:10 山頂には4組のグループが居て賑やかだった。 |
 |
11:21 ベンチがちょうど空いたので腰を掛けて昼。 剱岳は真っ白に冠雪してる。 富山湾方面もすこぶる景色が良い。 風もなく穏やかな山頂! |
| 写真無し | 12:05 下山開始、先へ進まず来た道を戻る。 いつも周回をするので、ここの下山は新鮮だった。 12:42 登山口へ戻る |
 |
少し時間があるので、大観峰へドライブ 展望台から先ほどまでいた山頂と剱岳を撮る。 八尾から来たというご婦人2名と出会って、山座同定をし合った。 彼女等は昆虫王国から歩いての往復だった。 この日のここからの剱岳は奇麗だった。 |

2019年4月23日
2019年4月23日
春山散歩
同行者ご婦人2名
友人に誘われて春山散歩に行ってきた。
コースは大岩登山口〜城が平山〜峠山〜はげ山〜峠山〜浅生分岐〜花の家〜大岩千巌渓〜大岩登山口
の周回ルート。
春の芽吹きが感じられて、爽やかなスタート。数回の休憩をはさんでゆっくり登る。
途中ゼンマイや、タラの芽、コシアブラなどを摘みながらゆく。
 |
9:00 大岩水公園駐車場集合 9:13 登山口 9::34 上の平 9:50 尾根に乗る 山頂手前の最後の階段 |
 |
10:30 城ヶ平山山頂! 快晴なのだがもやっていて視界は今一 それでも久々の山頂に満足顔の二人 Yさんは初めての山だった。 |
 |
11:24 山頂を越えて、尾根伝いにはげ山を目指す。 途中の峠山を越えてから西種集落が見えた。 トレイルラン数人と行き交う。 |
 |
はげ山への登り。手前に日影があった。 |
 |
11:40 はげ山山頂。 二人の先行者があった。既に食事中 私達も山頂の木の陰で食事。 13:00 スタート 下山に掛かる |
 |
13:25 浅生分岐地点を下る |
 |
13:45 花の家に立ち寄り、トイレタイム(無人) |
 |
14:30 大岩に下り千巖渓に立ち寄る |
 |
谷間にある祠で涼む二人。 14:40 登山口に戻る。 |

2017年4月17日(月)
2017年4月17日(月)
友人に誘われて
先輩スキー教師の仲間に誘われて地元の山にやって来た。
初めての山と言う喫茶店のオーナーを伴っての山行である。
 |
9時半過ぎに大岩親水公園駐車場で待ち合わせ 川下に目をやると桜が満開で艶やかに山裾を彩っている。 |
 |
登山口から水場を過ぎ、尾根道に出ると椿の群落が続く |
 |
乾いたルートを、山菜を探しながらチョロチョロと行く |
 |
75才となった先輩 |
 |
海も山もなんでもござれの先輩 |
 |
喫茶のオーナー |
 |
11時過ぎ、山頂に行いた。 |
 |
早速、宴会 高曇りで風もなく快適。 |
 |
剱岳をバックに贅沢なひと時 |
 |
12:30先へ進む |
 |
花の家に立ち寄りトイレ休憩。 |
舗装道路を下り車に戻りました。

2011年4月24日(日)
2011年4月24日(日)
友人と山菜摘み散歩
雨天予報が急に晴れ予報。近くでお手軽な山行きとなった。
はげ山までの往復をもくろんでスタート
同行者は山仲間の女性二人。勇んで出掛けたまでは良かったのだが〜
 |
8:00 大岩の駐車場にて集合 数台の車が停車している。 |
 |
今年は雪解けが遅く、谷筋の日陰には残雪がある。南向きの斜面はようやく春の訪れを感じさせている。 登山口で下山して来た青年に「雪はありませんと」聞き、歩き始める。 大岩川を渡り、斜面に差し掛かると山菜が目に付く。初手から山菜採り。 女二人に、猿回しのように(あっち!こっち!)と指図されながら斜面を徘徊する。カメラを水に落とすなどこちらは大損害なのに! ワラビ、ゼンマイ、蕗の薹、タラの芽、を収穫。 |
この山の一番の特徴は、椿の花が多くて 目を楽しませる空間のある事である。 前回は解説者が同行されたので、その種類が 特定されたが今回は良くわからないまま受け 売りの解説。 雪椿、寒椿、春椿? 一重、二重、八重 深い艶のある緑の葉に赤い花が見事である。  |
デジカメが使えないので、結局 城が平山頂前後の写真が無い。 10:00頃 山頂446Mで一旦休憩。ガスっているが視界は良好。富山湾も見えている。反対側の山は山頂にはガスが覆い剱岳は麓のみが見えている。 風が冷たいので早々に、はげ山方に向かう。 一応、地図を広げ、磁石で方向をセットする読図練習。 (以後は携帯写真) |
 |
11:00頃 峠山477Mに着く。途中倒木があり薮を迂回するなどしながら登り着く、はげ山が直ぐ目の前だった。誰とはなしにここまでにしよう!となり山頂で風除けにツエルトを張り昼。 持ち寄った食材で昼。 水上集落と種集落が真下に見えて野火の煙が穏やかにたなびいている。 昼にしていると、時々登山者が通り過ぎて行く。この日も7.8人の人に出会った。はげ山から城が平へ往復する人が多かったようだ。 12:25 その後一旦戻り、中間地点の鞍部から中浅生へ下る |
 |
13:00 杉林を抜けると耕作放棄田に蕗の薹が目を出している。再びザックを置いて山菜採りだ。 あぜ道を歩いて行くと、カモシカがこちらに気づいて、離れて行く。 彼も蕗の薹の新芽を好んで食べていたようだ。 |
 |
13:19 椿や山菜を片手に道を行く |
その後、浅生集落の山崎正男宅に立ち寄るが。「どうぞお気軽にご利用下さい」と玄関先に書き置きがある。
この山崎宅は今は無人で、無料で開放されている。誰でもが利用できるようにトイレも簡易水洗となっている。
このお宅の隣にある敷地の建物が今年の雪で半壊している痛々しい姿を見る。
まるで3月11日に起きた、東北地震津波の場面を想像させた。
人の気配も無いのでそのままアスファルトを大岩不動まで下り、境内にある目薬のお茶を頂き下る。
こうして、雨予想の一日を得したように終えたのでした。

2010年3月7日(日)
2010年3月7日(日)
郷土の歴史を訪ねる「探勝ウオークの会.大岩茗荷谷山」
友人から誘われ古里を訪ねる山歩きに参加した。わが恩師が講師をされると聞いたので
懐かしさもあり、また地元でありながら登ったことがなかったので良い機会だった。
 |
8:50 上市町大岩山日石寺の手前にある「大岩親水公園」 の広場に集合 講師の先生から、日程の説明とコースガイド の地図をもらう。 13人の人が集った。 半数は見知った友人達だった。 念のために荒縄とスコップを持ってゆくと言うので 私が持つことに |
 |
9:30 登山口の「大岩山バス停」へ向かう |
 |
バス停には公衆トイレがあるので用を 済ませて、 いざ出発! ちょうど大岩山日石寺の門前のお店が 居並ぶ所。 |
 |
9:37 大岩川を渡るとすぐに軽い登りにかかる 先生の説明も丁寧で、すぐに止まるので 汗をかく暇もない。 この辺りの地層から植物まで〜 メモ帳を片手に皆聞き入っている。 おまけに付近で草刈りしている人から (熊の足跡があるから気を付けて!)〜と |
 |
9:55 上の平に付くと、この一帯に集落があり 水が引いてあり、ここの住人が上の砦を護っていた と説明があった。 戦国時代の話も聞いた。 その後、近年になって一部の住人が平野部の 新屋と言うところに移り住んだと言う。 |
 |
10:26 寒椿と雪椿と恩師 尾根にかかると椿が咲いていた。 |
 |
10:30 前方に山頂が見えてきた。 雪もなく快適 |
 |
10:45 最後の急登。よく手入れが出来ている。 |
 |
10:55 山頂は流石に見晴らしがよい。 若干雪が残っていた。 富山市内から来たと言う団体さんや数人の方が 弁当を広げていた。 |
 |
平野部が一望 |
 |
11:36 山頂での記念写真 ナチュラリストのS氏としばらく振りに会った。 軽く昼食を食べてそのまま先へ |
 |
12:16 下り始めると残雪があり注意して下る 下ると、昔の鳥山後地に出て、、その昔 ここへ来て鳥を捕って食べたと地の利の良さを 語っておられた。 分岐から右へ下ると再び杉林へ (直進すると兀山へ通ずる。) |
 |
12:34 杉林を出ると山道は雪の下。 あぜ道のように雪を拾い林道に向かう |
 |
12:42 林道に出た所は中浅生部落。 取り付きにこの遊歩道を開拓された方の名が 付いている、(正男新道) |
 |
道を横切ると正男さんの生家があり、今は 無人となっている玄関を明けて、奥さんが 迎えてくれた。 大きな民家で立派な舘だった。 囲炉裏を囲んでしばし昔話を聞いた。 13:05 その後私は用事があるので一足先に大岩 へ下った。 |